こんな方におすすめ
- 発音がうまくできない
- 発音しても相手に通じない
- 発音の練習方法を知りたい
こんな方向け。
この記事でわかること
- 中国語の発音が40代の日本人にむつかしい最大の理由
- 中国語にあって日本語にない概念とは?
- 初心者が発音練習方法を解説【超簡単】
大家好。我是红莲。
こんにちわ紅蓮です。
発音がうまくできずに悩んではいませんか?
それ練習方法がわかっていないからかもです。
そこで今回は、歴20年の僕が発音の練習方法についてお話ししましょう。
この記事を読み終わるころには、うまく発音できる方法を知っているのでぜひ最後までお読みくださいね
記事の信頼性

中国語の発音が40代の日本人にむつかしい最大の理由
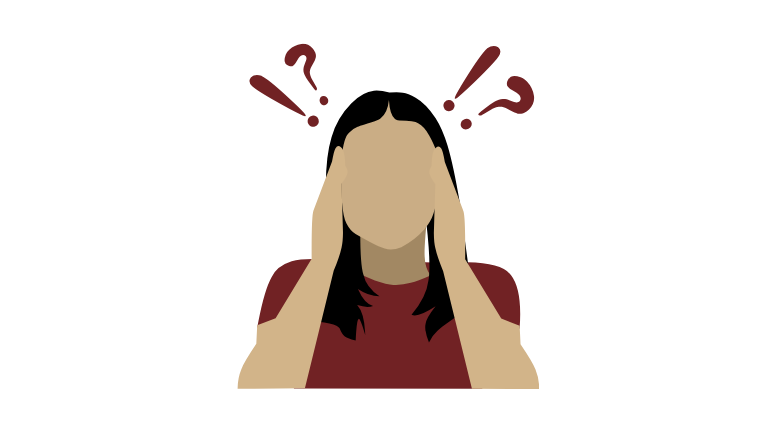
中国語の発音が40代の日本人にむつかしい最大の理由は、日本語に存在しない概念があるからです。
中国語にはたくさんの日本語にない概念が存在します。そしてほとんどの人がその概念に戸惑い、挫折していきます。
例えばウムラウトの発音。日本語には口をすぼめたウを発音することはありますが、口を横に引いて、うの発音をするという音の概念はありません。
僕自身20代から勉強を始めて20年以上になりますが、いまだに概念の違いにおどろかされます。
そのため、ほとんどの40代の初心者の中国語学習者はむつかしく感じると思います。
中国語にあって日本語にない概念とは?

中国語にあって日本語にない概念は、以下の通り。
- ウムラウト
- 声調変化
- ピンイン表記
- 有気音と無気音
- 反り舌音
- 軽声
それぞれ解説していきます。
ウムラウト
中国語にあって日本語にない概念の1つ目はウムラウトです。ウムラウトとは、「エ」という口を横にひいた笑顔の口で「ウ」という特殊な発音です。
これは日本語にはない特殊な発音で、僕の中国語仲間でも戸惑う人はたくさんいます。
僕自身もここではかなり戸惑い、学習の手が止まってしまいました。
むつかしく感じるポイントのベスト3に入るところですね。
ポイントに関しては、下記記事にて詳しく解説しているので是非参考にしてくださいね
》ウムラウトのポイントを詳しく解説【練習方法も】
声調変化
中国語にあって日本語にない概念の2つ目は、声調変化です。声調変化は四声とも呼ばれ、抑揚をつけて、同じ音でもイントネーションで何の意味かを図るという方法です。
日本語でいうところの「箸」と「橋」の違いのようなものといえます。
基本は発音がこの声調変化がうまくいかないと意味が通じないようになっているのです。
こちらもむつかしく感じるポイントベスト3に入りますね。
声調変化に関しては、下記記事にて詳しく解説しているので是非参考にしてください。
》声調変化とは(四声)【練習方法も】
ピンイン表記
中国語にあって日本語にない概念の3つ目は、ピンイン表記です。ピンイン表記とは、簡易の上や下に降られるアルファベット表記のことです。
日本語のルビがこれに当たります。
ただ中国語を始めるとこのピンイン表記がありますが、中級になったり中国に行くとなくなったりします。
そのために中級になるに至ってどんどんむつかしく感じていくかもしれません
》ピンインとは。
有気音と無気音
中国語にあって日本語にない概念の4つ目は、有気音と無気音です。有気音と無気音とは発音するときにだす息のことです。
例えばご飯を意味する菜(cài)は有気音で、強く息を吐くように「ツァハーイ」という感じです。無気音にはお姉さんを意味する姐姐(jiějiě)と息が入らないようにゆっくりと明確に「ジエジエ」と発音します
これができていないとまったく意味が変わってしまうので注意が必要です。
こちらも意識をしていないとむつかしく感じる場所ですね。
有気音と無気音の練習方法
練習方法は、以下の通り
- ティッシュペーパーを顔の前にたらす。
- 有気音を発音して、前に勢いよく行けば有気音OK
- もしいかなかったら、有気音になっていないという感じ
- 無気音は、逆に勢いよく言ってはいけないので丁寧に言うように気を付ける
詳しい練習方法に関しては、下記記事にて解説していますので、参考にしてみてくださいね。
》有気音と無気音の練習方法を詳しく解説【初心者の登竜門】
反り舌音
中国語にあって日本語にない概念の5つ目は、反り舌音ですね。反り舌とは、舌を丸めてそらすようにしてする発音方法のことです。
例えば、zhやchの発音がそうですね。音の特徴としては、ちょっと息がこもった感じになります。本当にを意味する「真」は「ヂェン」とちょっと濁った感じになります。
これもできていないと、認識の違いが発生します。
むつかしいもののベスト5にははいりますね。
反り舌音の練習方法
練習方法は以下の感じ。
- 手鏡を口の前でもって、rの発音をする
- そのときに、舌がどこにもついていないことを目で確認
- その状態でzh,sh,chなどの練習もする
詳しい練習法は下記記事にて解説しているので是非参考にしてしてくださいね。
》反り舌音の練習方法をプロが指導
軽声
中国語にあって日本語にない概念の6つ目は、軽声です。軽声とは妈妈(māmā)のように同じ単語が重なったときに変化の時に2つ目の母音が軽く読まれるという法則のこと。
例えば先ほどご紹介した、お姉さんを意味する姐姐(jiějiě)もおなじで、2つ目のjieに関しては軽く読まれるように変化をします。
こちらもちゃんとできないと間延びした中国語になってしまうため注意が必要です。
中国語がうまくなるには大量に発音しか方法がない


そうは言われてもむつかしいよ。
そう思っている人もいるかもしれません。
そんなあなたに言うべき言葉は、発音はもう大量にするしか方法がないことなんです。
この時に重要なのは突っ込み役を必ず用意することです。というのも、間違いに気づかないといけないからです。
せっかくの発音も相手に通じなかったら、意味がありませんよね。
ミスってしまって認識の違いがあると大変なことになります。
必ず突っ込み役を用意するようにしましょう。
初心者が発音練習方法を解説【超簡単】
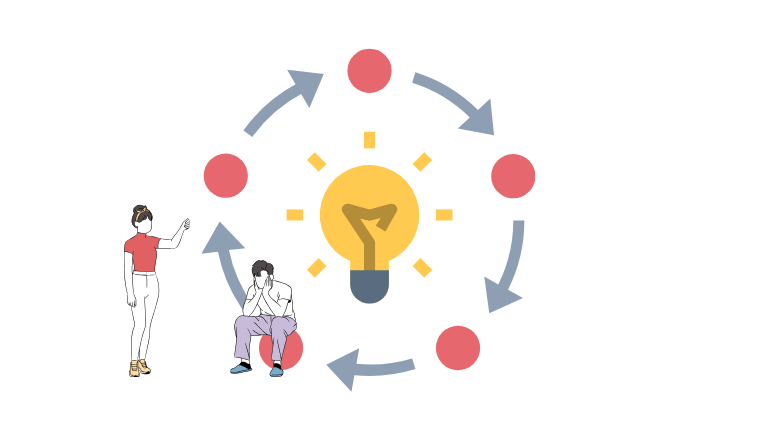
発音練習方法は以下のステップで行うと効果的です。
- 音声付きの本を買う
- 音声を聞く
- 真似る
- 録音して確認する
それぞれ解説していきます。
音声付きの本を買う
発音を正しくするための練習ステップの1つ目は、音声付きの本を買うことです。
本の種類に関しては、会話本でも単語でも問題ありません。
音声が真似られるならなんでもOKです。
音声を聞く
発音を正しくするための練習ステップの2つ目は、音声を聞くことです。
買ったら音声を聞きましょう。
この時のポイントはなるべく集中できる状況下で聞くこと。
というのもBGM代わりに聞いて、ペラペラになった人を僕は知りません。
そのために聞き流しをやめて集中するようにしましょう。
マネる
発音を正しくするための練習ステップの3つ目は、マネることです。まねるとアウトプットになるから。
もしまねしないと、聞き流しと変わりがありません。そのため、真似られる状況下で練習するようにしましょう。
録音して確認
発音を正しくするための練習ステップの4つ目は、録音して聞くことです。というのも間違っているのに気が付くため。
初心者の時は大体の場合、発音が間違っています。そのままにしてしまうと、間違ったままになってしまい、認識の違いが発生するかもしれません。
いうときにはなるべく録音して、音声との違いを理解するようにしましょう。
まとめ|どんどん話して間違って、うまくなろう
お疲れ様でした。
ここまで発音がむつかしいところ、日本人にない概念、発音方法とお話してきました
最後に発音自体はもう数をこなすほかありません。というのも反復するしか方法がないのです。
ミスを恐れずにたくさん間違って正しい発音をできるようになりましょう。
今回は以上です
